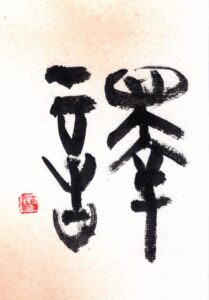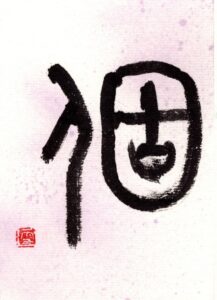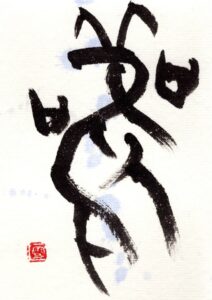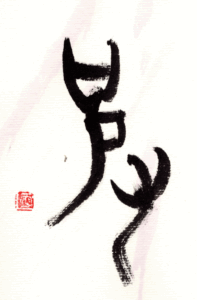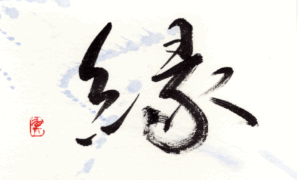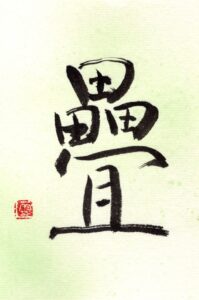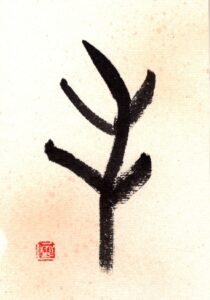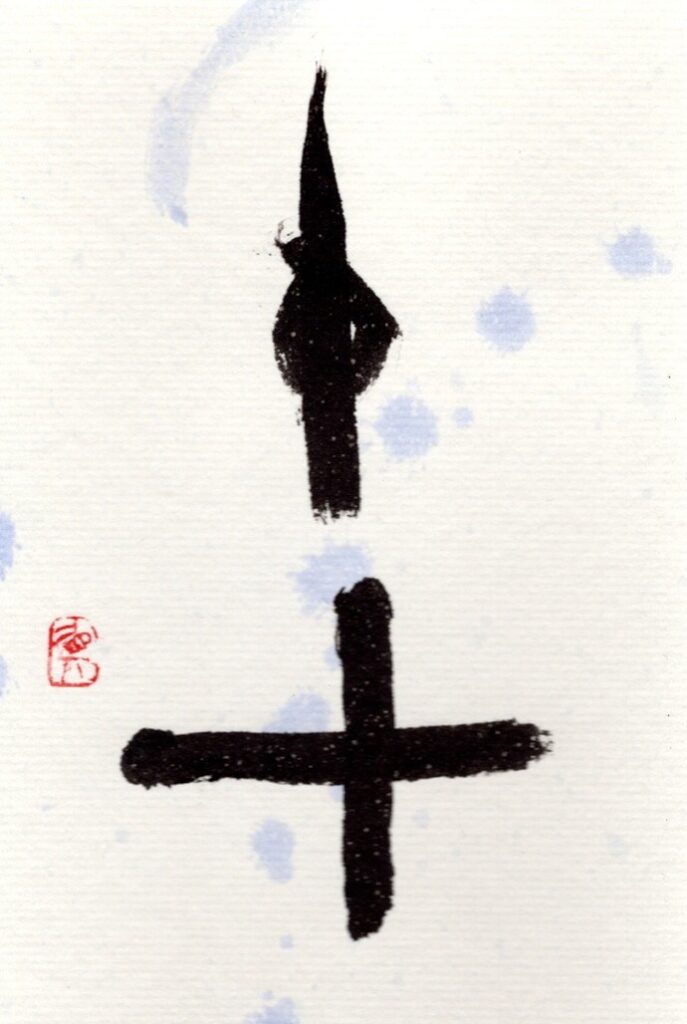
文字の成り立ち 【十:指事】数を数える時に使う算木で数を表したので、横1本が一、縦1本が十となる。【七:仮借】もともとは切り取られた骨の形で、その音を借りて数の「しち、ななつ」に使う。
漢字の成り立ちは、大きく分けて以下のように説明できます。
- 象形文字(しょうけいもじ)
ものの形を絵のように表したもの。
例:「山」「川」「木」 - 指事文字(しじもじ)
記号的に形を工夫して、抽象的な概念を表したもの。
例:「上」「下」「一」「二」 - 会意文字(かいいもじ)
意味をもつ漢字を組み合わせ、新しい意味を表したもの。
例:「林」(木+木)、「休」(人+木) - 形声文字(けいせいもじ)
意味を表す部分と、音を表す部分を組み合わせたもの。
漢字の約7割がこれ。
例:「河」(氵=水の意味+可=音) - 転注文字(てんちゅうもじ)
本来の意味から転じて、別の意味で使われるようになったもの。
例:「楽」(音楽→楽しい) - 仮借文字(かしゃもじ)
もともとの意味と関係なく、発音を借りて別の意味を表すようになったもの。
例:「来」(もとは麦の象形→音を借りて“くる”の意味に)
この6つをまとめて 「六書(りくしょ)」 と呼びます。
詳しい話はご専門の先生方にお任せして、文字の形や書の線のオモシロさを楽しんで書いています。漢字の古代文字(甲骨文字・金文)も、まだまだ新しい発見がありそうでワクワクします。文字が生まれてくる時のパワーを感じてみてください。